イスラエルへ出かけるというと、周りの人たちはみな一様に心配そうな表情を見せる。「大丈夫?」「ロケット弾が飛んでくるんじゃあないの?」「無事に帰ってこられる?」
確かに戦争やテロはイスラエルで何度も起きている。十数年前初めて訪れたときは、パレスチナ人による暴力による抵抗運動「インティファーダ」(第2次)が始まって間もない頃で、観光客は目に見えて少なかった。昨年の夏も一時期ガザ地区からイスラエル国内へロケット弾が頻繁に打ちこまれ、人々はサイレンが鳴る度に防空壕へ駆けこんだという。イスラエル軍もガザ地区に侵攻、攻撃して、多くの人が死んだ。秋に予定していた2度目の訪問はできないのではと、一時私自身が思った。
しかし一旦イスラエルへ入国すれば、ヨルダン川西岸の一部地域などに足を運ばないかぎり、危険は感じない。今回世話になった大使館の女性職員は、赴任以来一度も身の危険を感じたことがないと語っていた。私も1度、安息日が終わった土曜日の夜、ホテルを出てテルアビブ市街を一人で歩き回ったけれど、大勢の若者が外へ出て、洒落たレストランで食事をし、開放的なバーでビールを飲み、屋台風の店でサンドイッチやジュースを買って楽しんでいた。
最初の訪問時と比べ、今回訪れたイスラエルは明らかに豊かになっていた。テルアビブやハイファ、そして多少雰囲気の異なるエルサレムでさえ、高級ホテルが立ち並び、ブティックやレストランが軒を並べる。地中海ぞいのテルアビブとその近郊のヘルツェリアなどは、一瞬南カリフォルニアのリゾート都市と錯覚するほどである。
私が滞在したホテルは、そのテルアビブの海岸沿いに立っていた。毎日階下のレストランで、ブッフェ方式の朝食が供される。野菜、果物、ジュースはどれも新鮮で歯ごたえがあり、パンやチーズは多種多様で日本にはない種類が多い。たくさんの乾燥果実、ナッツ類、魚の薫製、各種のオリーブなどが豊富に並ぶ。ユダヤ人独特の見慣れない食べ物もあるけれど、全体的には地中海地域の自然の恵みを感じさせる食材に満ちている。
ユダヤの料理はあんまりおいしくないと、先回イスラエルを訪れたときは思ったけれど、豊かになった今日のイスラエルでは、周辺中東地域の料理から影響を受けた多様な食文化が花開いている。ハイファで食べたアラブ料理はうまかった。ちなみにエルサレムのある小さな立ち食いの店で出す、ピタパンのサンドイッチは絶品です。ファラフェル(ひよこ豆を水でもどしすりつぶして香辛料を加えて揚げた、がんもどきのようなもの)と野菜をはさみ、好みに応じて辛いソースをかけて食べる。第1回の訪問で初めて訪れ、その味が忘れられず今回再訪した。店は場所も味も変わっておらず、古い友人に会ったように嬉しかった。
ホテルの朝に戻ろう。一人で座る私は、運んできたサラダやパンを食しながら、まわりにいる他の客の姿を観察する。海を望む大きな窓からも、海岸の遊歩道を散歩する大勢の人が見える。イスラエルを訪問中のアメリカやヨーロッパのユダヤ人をふくめ、その多くはユダヤ人であるはずだが、同じ民族であっても、人によってずいぶん容貌や体格が違う。その多様性は最初のイスラエル訪問のときよりも、ずっと目立つように感じたが、目が慣れたせいだろうか。
もちろんアメリカでつきあっていた多くのユダヤ系アメリカ人と同じ、北ヨーロッパ系のユダヤ人(アシュケナジーと呼ぶ)は多い。遠目で見ても、あの女性は昔大学でクラスメートだった子にそっくりだ、法律事務所で一緒に働いた弁護士の誰それと同じ顔だ、もしかしたら親戚かしらんと、なつかしさの混じった不思議な感動がある。
しかしたとえばロシアから移住してきたユダヤ人は、かなり異なる独特の雰囲気をもっているし(彼らの多くはイスラエルに来てからもロシア語を話している)、地中海沿岸地域や中東から移住してきたユダヤ人(スファルディと呼ぶ)も、受ける感じが違う。さらに皮膚の黒い人たちも目立ち、彼らはおそらくエチオピア出身のユダヤ人である。これら後からやってきたユダヤ人たちは、建国期に中心的役割を果たしたアシュケナージと比べ、イスラエルにやってきた当初は貧しく教育もなく、それゆえに差別も受けた。しかしイスラエルで生まれた彼らの子供たちが、今や急速に政治的、経済的、文化的影響力を増している。一口にユダヤ人国家といっても、その内部での相互の関係は複雑である。
それでもなお、遠い祖先、歴史、宗教、流浪の苦難を共有する彼らは、2000年近く前に追われた古代ユダヤ王国の土地に近代国家を築く。幾多の戦いに勝利して独立を保った。また世界各地から流浪を続けていたユダヤ人の同胞を無条件で受け入れ、荒野を肥沃な耕作地に変え、ハイテク技術を開発し、今日の繁栄をもたらした。イスラエル建国から現在までの歴史は、彼らが誇って当然のものである。
けれどもあらゆる成功には代償が伴う。建国から70年近くかけて築いた安全と繁栄を維持するために、この国は相当無理をしている。ホテルの部屋の窓から海を眺めていると、朝早くから軍用ヘリコプターがしきりに海沿いを低空で飛びすぎる。双発のプロペラ機も飛んでいる。あれは海からの侵入者がいないかどうか、警戒しているのだろう。ハイファの町のカフェで休んでいたら、上空をジェット戦闘機が轟音と共に飛び去った。緊急発進をしたのか、どこかに爆弾を落としに向かうのか。内戦のただ中、イスラム国の兵士が跋扈するシリアは、東の方向に横たわるゴラン高原のすぐ向こうにある。
そして何よりも、次々に建設される壁の存在がある。1967年の第3次中東戦争でイスラエルが占領したあと、東エルサレムに建設された新しいユダヤ人入植地を取り囲むかたちで、厚く頑丈な壁が続く。パレスチナ暫定自治区の首都ラマッラーやキリストの生誕地ベツレヘムレなどへ行くには、検問所を通ってこの壁の向こう側へ出ねばならない。検問所を出て振り返ると、壁にはたくさんの落書きがあり、そのなかには天の神が困惑したような表情で地上の混乱を眺めているものもあった。
こうした壁やフェンスはイスラエルとガザの境界線をも完全に包囲し、ヨルダン川西岸地区では新しいユダヤ人の入植地の周りを囲むかたちで建設されている。この背景にはイスラエル国内でたびたびテロ事件を起こすパレスチナ過激派の侵入を防ぐという2002年にはじまった政策があるのだが、壁のためにイスラエル国民とパレスチナ人が日常的に接する機会が減り、それがまた相互の不信感と嫌悪感を深めているという。
英語にゲットーという言葉がある。都市の貧民街の意味で使われるが、もともとは中世イタリアの交易都市ヴェネチアのユダヤ人居住区を指す言葉であった。金融や貿易に長けたユダヤ人は、ヴェネチアの経済発展に大いに貢献したのだが、キリスト教徒でない彼らは周りを高い塀で囲まれ水路で仕切られた地区にしか住むのを許されなかった。ヨーロッパのユダヤ人がこうした隔離状況から解放され各国の市民として活躍するようになったのは、フランス革命・ナポレオン戦争以降である。
こうした歴史を振り返る時、かつて少数民族としてヨーロッパで迫害され壁のなかに押し込められたユダヤ人たちが、今やその優越的な立場を利用して自分たちを壁で取り囲み、パレスチナ人を入れようとしないのは、やや皮肉な事実であるように思える。それにいくら壁で自分たちを囲っても、イスラエル国民の約20パーセントはもともとこの地に住んでいたアラブ系の人たちである。彼らはイスラエル市民として人権を守られているものの、ユダヤ人市民とのあいだにはやはり緊張があり、差別があり、実質的に2流市民の地位に置かれている。壁のなかにまた壁がある。
蛮族の侵入を防ぐために、中国人は万里の長城を建て、ローマ人はハドリアヌスの壁を建てたが、あまりうまく行かなかった。壁こそ建てなかったものの、日本人も二世紀以上鎖国して、結局開国を強いられた。ベルリンの壁はやがて崩されたし、今日のアメリカ合衆国もメキシコとの国境線の一部に壁を築いて不法移民の侵入を防ごうとして、なかなかうまくいかない。
アメリカの詩人ロバート・フロストは、Mending Wall(壁の修理)という自作の詩を、 “Something there is that doesn’t love a wall”(そこにある何かが壁を嫌っている)という言葉で始めている。春になって隣人の土地と自分の土地を隔てる石垣を、2人で点検して回る。壁なんてなくてもよいのではとフロストがいうと、隣人は “Good fences make good neighbors”(よき壁がよき隣人をつくるんだよ)と言い返すという内容である。
世界中を流浪し、差別や迫害に耐えながら、固い一体感と高い能力で何千年も生き抜いたユダヤ人が、ようやく築いた先祖の地で自分たちをかたくなに壁で囲い、かえって国際社会で孤立している。中東という荒ぶる地域の真ん中でゆくには、これしか方法がないのだろうか。いつかこの政策は破綻しないか。
現代のイスラエル情勢は複雑すぎて、十数年でたった2回訪れただけで理解できるようなものではない。しかしやはり訪れてよかったと思う。実際に行かなければわからないことがたくさんある。そしてこれからイスラエルへ旅をしてみようと思う人、またイスラエルに興味のある人には、手はじめに『イスラエルを知るための60章』という本を読むように勧めたい。
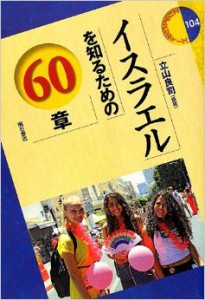
『イスラエルを知るための60章』(明石書店、2012年)
本書はイスラエルの専門家が分担して、この国の背景、歴史、現状、日常生活、社会構造、政治と安全保障、経済、文化、外交などについて、わかりやすく、しかしかなり深く説明している。記述は時にイスラエルの国民にやさしく、また時には批判的である。著書の一人に教えられて今回出発前にこの本を読んで、どれだけ私の理解が深まったことか。
日本への帰路に着く前、ベングリオン国際空港のロビーにあった店で、2枚のCDを買った。1枚はイェメンから移住してきたユダヤ人のあいだに伝わる伝統的な音楽をアレンジしたもの。もう一枚はリビアから移住してきたユダヤ人の音楽である。近年こうしたオリエント・ミュージックと呼ばれるジャンルが、イスラエルの若者のあいだで人気が高いのだそうだ。日本に帰り、ときどき2枚のCDを聴きながら、イスラエルで出会った人たちを思い出している。
テルアビブのホテルで一緒になった赤ん坊連れのユダヤ人の若い母親たち。子供は天の宝よと口々に言っていた。ハイファのカフェでサブラフという伝統的なアラビアの乳飲料でもてなしてくれた、人なつこい店長。エルサレムの墳墓教会、日曜日のミサでアラビア語の説教を聴きながら祈りを捧げるパレスチナ人のカソリック教徒たち。ハイファの北、十字軍が上陸して築いた城塞都市アッコのシーフードレストランを切り盛りする、哲学的なオーナー。彼らはその後どうしているだろうか。
阿川尚之(あがわ・なおゆき)
慶應義塾大学総合政策学部教授。1951年4月14日、東京で生まれる。慶應義塾大学法学部政治学科中退、米国ジョージタウン大学外交学部、ならびに同大学ロースクール卒業。ソニー株式会社、日米の法律事務所を経て、1999年から現職。2002年から2005年まで、在米日本大使館公使(広報文化担当)。2007年から2009年まで慶應義塾大学総合政策学部長。2009年から2013年まで慶應義塾常任理事。
主たる著書に『アメリカン・ロイヤーの誕生』(中公新書)『海の友情』(中公新書)『憲法で読むアメリカ史』(PHP新書)(ちくま学芸文庫)『横浜の波止場から』(NTT出版)『海洋国家としてのアメリカ:パックスアメリカーナへの道』(千倉書房)(共著)など。
撮影 打田浩一
